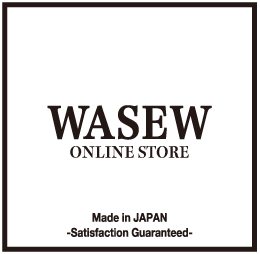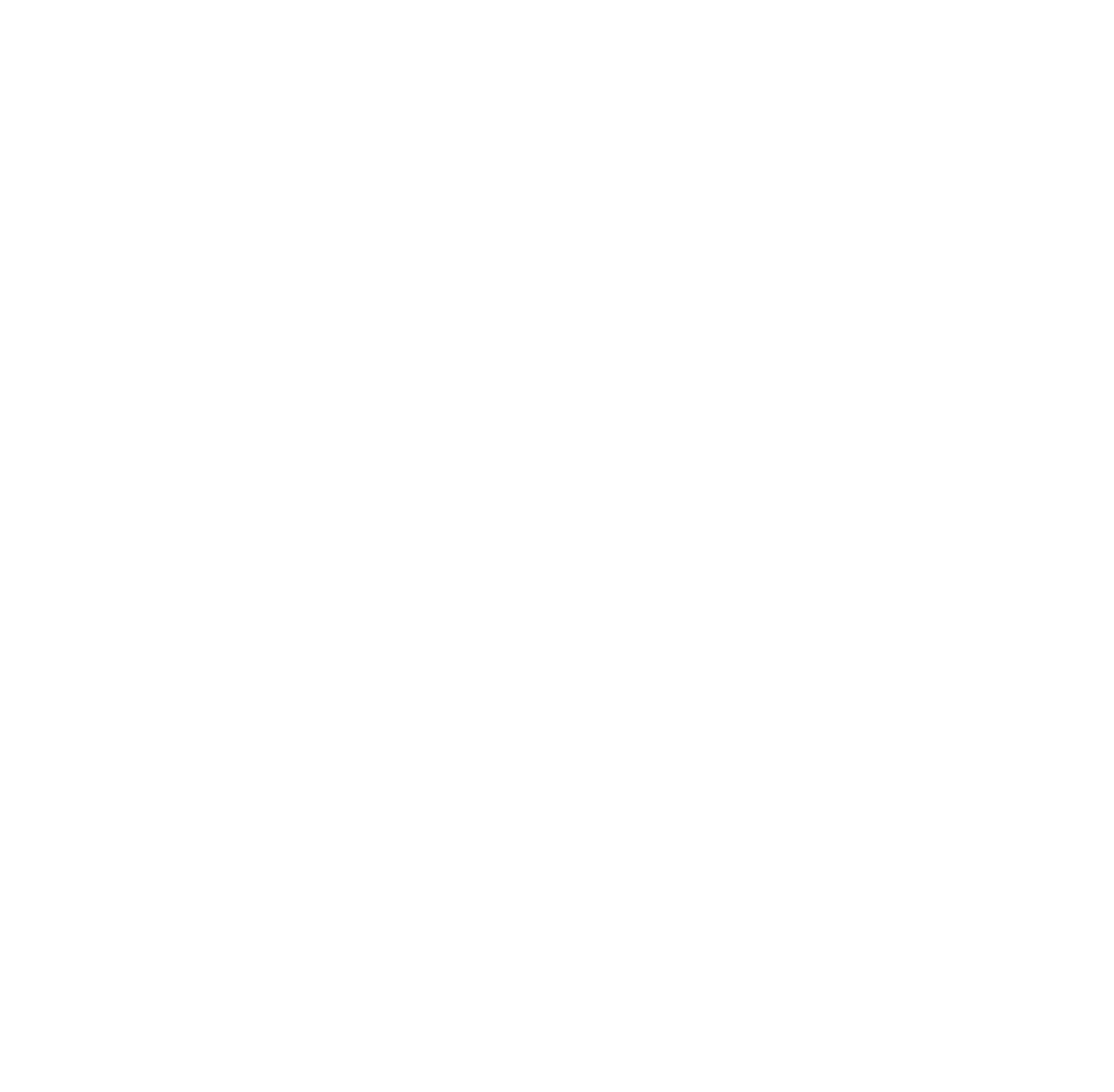1枚は持っていたい便利アイテム、サーマルシャツ。凸凹のユニークな生地で作られたこのシャツは、アメリカ軍やアウトドア愛好家の防寒着として重宝され発展してきました。この記事では、「サーマル」とは何なのか?これを歴史、生地、ファッションの観点から考え、その魅力を解説します。
-
歴史
・サーマルシャツの起源
・ファッションとしての発展 -
生地
・凹凸形状の理由 -
種類
・ワッフル構造
・ハニカム構造 -
WASEWが作る2つのサーマルシャツ
・GENKOTSU THERMAL
・MIL THERMAL
1. 歴史
サーマルシャツの起源

サーマルシャツの起源は定かではなく諸説ありますが、20世紀前後から寒冷地での活動において優れた防寒性を持つ機能的なアンダーウェアとして、アウトドア愛好家や軍隊によって使用され始めたというのが一般的です。
実際に戦時中、寒冷地で従事する兵士たちへ支給されていました。ミリタリーアイテムは過酷な状況で使用されるため、高い機能性が求められます。これまでも様々なものを発展させてきましたが、サーマルシャツも代表的な一つといえるでしょう。
ファッションとしての発展

軍のユニフォームが起源となるトレンチコートやピーコートなどとは異なり、初期のサーマルシャツはデザイン性よりも防寒アンダーウェアとしての機能性を重視していました。そのため、ファッション性はほとんどなく、ただの下着という位置づけだったのです。

そのユニークな見た目と構造が注目され、やがてミリタリーやワークウエアの文脈からカジュアル/デイリーユースのアイテムへと変化していきます。  現在では、1枚で着るロンTとしても、レイヤードアイテムとしても選ばれるスタイルの定番になりました。
2. 生地
凹凸形状の理由

サーマル生地の最大の特徴は「凸凹」の編み造形にあります。凸の部分が肌に触れ、一方で凹の部分にはわずかな空気の層が生まれます。その空気層が体温によって暖められ、シャツ内に“暖かな空気を纏う”ような保温効果が生まれます。  また、伸縮性や肌あたりも凹凸構造が影響し、「単に厚手=暖かい」というだけではない、軽やかな着心地とのバランスも生み出されています。
3. サーマル生地の種類
ワッフル構造

最も一般的に「サーマル」と聞いて連想されるのが、このワッフル構造。凹凸が浅めで、比較的軽く、1枚でインナーにもアウターにも使いやすい仕様です。WASEWの「GENKOTSU THERMAL」では、和歌山/吊り編み機に近い「ゲンコツ機」で編まれたオリジナルワッフル生地を採用し、伸び・型崩れの少なさにもこだわっています。
ハニカム構造

もう一つ、注目すべき構造が「ハニカム構造」です。こちらは凹凸が深めで、空気層がより豊かに保持され、厚みと保温性を備えた仕様となります。WASEWの「MIL THERMAL CREW NECK」では、太番手の空紡糸を用い、度詰めで編み立てたハニカム構造によって「安心感のある厚み」と「タフな着心地」を実現しています。
4. WASEWが作る2つのサーマルシャツ
GENKOTSU THERMAL(ワッフル構造)
和歌山のゲンコツ機で編み立てたオリジナルワッフル生地を用い、吊り編み機に近いゆったりとしたテンションで編むことで、柔らかな肌あたりと伸縮性に優れた着心地を実現しています。  シルエットは1枚でも着られるよう“程よく身幅をもたせた”仕様。フラットシーマによる縫製で縫い代の肌干渉を抑え、レイヤードでも快適です。

MIL THERMAL(ワッフル構造)
ミリタリー由来の機能性を現代に落とし込んだ、太番手空紡糸×ハニカム構造の肉厚サーマル。度詰めで編み立てているため型崩れしにくく、着込むほどに馴染んできます。  縫製はバインダーネックとフラットシーマを採用し、縫い目による違和感も軽減。インナーとしても、1枚で着ても成立するインパクトと質感を備えています。

「質」にこだわったサーマル
どちらのモデルにも共通して言えるのは、「派手さではなく丁寧さ」「機能ではなく佇まい」「トレンドではなくルーツ」の美意識。編み機・素材・縫製といった“細部”に手を入れることで、見た目はシンプルでも、着るほどに愛着が増す一着となっています。 長く愛せる服を探している方にこそ、ぜひ選んでいただきたいシリーズです。